2018年: 工藤日出夫議会レポート / 会派・市民の力 機関紙
工藤日出夫 北本市議会レポート 第141号(2018年1月)

あけましておめでとうございます。
皆様にとって、今年一年のスタートです。安心できる、幸福な生活を願っていることと存じます。
私も、平成15年の初当選から15回目の新年を迎えました。ここまで長く勤められたのは、市民のみなさんのご理解のたまものと改めてお礼申し上げます。今年も、皆様の暮らしに係る政策の推進に勤めます。
年頭所感: 普通に暮らせる普通のまちへ
減り続ける人口に打つ手なし
私が初当選した平成15年の選挙は、市長が石津賢治さんに代り、国主導の市町村合併が問われた頃でした。私は、選挙公報で「無原則な合併」から「自立に向けた改革」を主張しました。
その後、北海道夕張市の財政破綻が起こり、財政改革が叫ばれ、借金財政に苦言を申し上げました。私が議員として、北本市の将来に疑問を持ち始めたのが、人口減少でした。北本市は、平成17年の約7万2千人をピークに、人口減少が起き始めています。転入者を転出者が上回る社会減が起きたのです。
私は当時の石津市長に「この現象が3年続いている。これに少子化による出生者数の減少が加わると、人口減少が構造的に進み、回復が難しくなる」と指摘し、対策を講じるように注文付けました。こども医療費の無料化や少人数学級の導入など、目新しい政策を推進しましたが、人口の転出超過は止まらず、出生者数の減少は加速し、人口が増加している埼玉県においては、人口減少先進地になり、その脱却が最重要課題になりました。
人口減少視野に終の棲家へ
石津市長を破り新市長に就任した現王園市長は、人口減少対策を柱にした「第五次総合振興計画」を策定しました。しかしながら、依然まちの将来像が見えてきていません。
私は、五次総の策定特別委員会委員長でした。提案された計画案は、現状(因果)の分析が不十分で、これまでの誤りを繰り返す可能があると、策定のし直しを主張しました。
石津市長時代から10年以上にわたり、人口動態への視点が欠けたままです。もはや人口は全国的に減少期に入り、これからは人口減少を視野に、住民が「終の棲家」として安心して暮らせる世の中にすることではないでしょうか。
それには、これまでの「古いしがらみ」から、市民一人ひとりと「新しい絆」へ変えていくことです。一人ひとりの市民が声を出し、政治に注文付けることです。お任せ民主主義から、住民自治(政治を監視)の市政に変えることです。
北本市の未来に、危機感を持っている人もいるでしょう。私は政治家(議員)として危機感を強く認識しています。根拠のない「成長政策」でなく、地に足を付けた「普通に暮らせる、普通のまち」に成長させることではないでしょうか。今年も住民目線を貫きます。
工藤日出夫 北本市議会レポート 第142号(2018年4月)
人口減少へ対応する予算審議の平成30年第1回定例議会終わる
第五次北本市総合振興計画の目標人口達成困難の見通し
北本市議会は、平成30年第1回定例会を3月22日全日程を終了し閉会しました。今定例会は、2月26日に開会し平成30年度一般会計並びに特別会計予算と条例等の議案が提案され、総括質疑、議案質疑、委員会審査において議論され、市長提出議案33件はすべて原案通り可決しました。
また、12月議会で否決された「深井グランドの買取り議案」は、再提案され可決しました。市民が出された請願2件は1件は採択、もう1件は一部採択という結果になりました。
一般会計予算 195億9,400万円 歳入の柱 市税は3憶2,400万円減収
平成30年度の一般会計歳入歳出予算195億9,400万円が可決しました。また5特別会計と1企業会計の歳入歳出予算も可決しています。このことで平成30年度の事業は滞りなく開始されます。
一般会計の市税収入は、87憶1,492万円で前年度より3億2,430万6,000円減っています。大手自動車製造会社の一部撤退に伴う影響です。
また、国庫金は微増したが、地方交付税は1億2,000万円の減でした。
市が公表した財政計画では、人口減少などの影響で市税は平成39年時の推計で70億円と7億円減収となる予定です。
新規事業で次の展望は
新規等重点事業は、人口減少対策としてのリーディングプロジェクトの若者の移住定住のための補助金や子育て日本一のこども医療費中学生まで無料、道路補修費、観光・交流人口に向けた事業(森林セラピー)があります。
また、桜国屋のリニューアルに向けた計画策定や産業振興ビジョンの改定なども計画されています。
特別会計では、今年度から県単位になった国民健康保険制度改正により、国民健康保険税の大幅な改定がありました。低所得者に配慮しているようですが、全体に引き上がっています。
市民の健康と命を守る社会保障制度であり、これ以上の負担感を高めることには慎重であるべきと考えています。
埼玉の人口減少先進市
現王園市長は予算案の提案説明で、「人口減少が今後も続くので、リーディングプロジェクトの着実な実施をする」と述べました。
しかし事業の若者移住の補助金やこども医療費無料化の対象拡大等の事業は、すでに他市においても行われており、これで人口減少を抑制できるかは、見通せていないようです。
答弁で市長は「第五次総振の目標人口の達成は困難である」との趣旨の発言をしています。
本市の人口減少は、平成17年から始まりここまで一度も改善されていません。まさに人口が増加していた埼玉県の市町で数少ない「人口減少先進都市」です。
確実に増やす又は抑制できるという合理的理由を持たないまま、貴重な財源を使うことは慎重であるべきです。
新しい成長戦略を
人口減少でも、住民の福祉を保障する。人口減少の中で新しい地域の経済社会をつくる。圏央道開通の新アクセスのメリットの開発研究をする。発想の転換でダブーに勇気をもって挑戦する。「しがらみや縁故主義」を見直し、新しい成長戦略を構築しなければならない時期に来ています。
私たち会派市民の力は、平成30年度予算(案)の賛成討論で、経済成長政策は、市の経済指標を構造的に分析し、リアリティーのある数値の裏付けのない事業には投資しない。人口減少は怖くない。小さくとも安全・安心の福祉が大きい北本市へ、どのように軟着陸させるか。住民と一緒に考える時が来ている。
「今でしょ」と申し上げた。
工藤日出夫 北本市議会レポート 第143号(2018年5月)
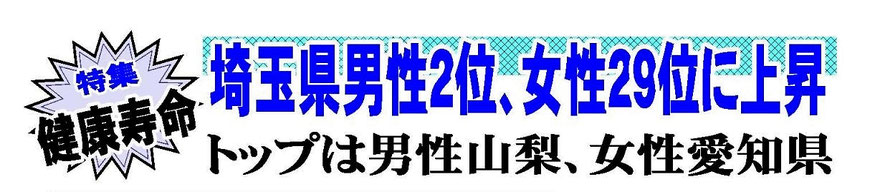
特集 : 健康寿命 〜 埼玉県 男性2位 女性29位に上昇
トップは男性 山梨県、女性 愛知県 〜 人生100年時代の健康寿命設計
日本の平均寿命は世界でもトップクラス。一方、寝たきりの数も世界有数と言われている。そのため単なる「長生き」でなく、「健康で長生き=健康寿命」が注目されている。厚労省は、2016年の健康寿命を公表した。
それによると、男性は山梨県73.21歳、女性は愛知県76.32歳が1位で、埼玉県は男性73.10歳で2位、女性は74.67歳で29位でした。
2013年男性は71.39歳(21位)、女性74.12歳(33位)から上昇しています。人生100年と言われ、一人ひとりが健康寿命の設計をつくることが長生きの秘訣のようである。
健康寿命トップスリーの秘密を探る
山梨県
山梨県は、冬寒く夏暑いと気候条件はよくないが、水がきれいで果物などの農産品がよく野菜の摂取量が多い。また、がん検診の受診率が高く、健康と医療に注目。
埼玉県
埼玉県は2025年に75歳以上高齢者の伸びが全国一。そこで県は「健康寿命埼玉プロジェクト」を開始。
毎日1万歩運動や筋トレを推奨。さらに1食当たりの塩分3ミリ以下、野菜130g等、健康レシピを推進している。
愛知県
愛知県は、健康的な食生活を呼びかけ塩分摂取量は減った。また、健康づくりリーダーを養成し、地域で健康づくりに取り組んだ。愛知県は、モノづくり王国で、働くことが健康の秘訣になっている。
目指せ県内トップ
埼玉県が独自に健康寿命(65歳の人が要介護2以上になるまでの年数)を推計しています。
それによると北本市は
- 男性17.52年(82.52歳)
- 女性19.94年(84.94歳)
です。男性は県内17位、女性は41位でした。(63市町村)
健康寿命を延ばす3種の神器は、
- 食事の改善(健康レシピ)
- 適度な運動(ウォークなど)
- 定期的健康診断(特定・ガン)
といわれ、一人ひとりの自覚(意識改革)が求められています。この3種の神器に、ストレスを減らす生活。北本市の特色である自然との関わり(森林浴など)、働くことを組み合わせると良いようです。
さあ今日から健康寿命大作戦!
大杉漣さんの悲劇
突然死を防ぐ
大杉漣さんの突然死には驚かされた。野村監督の妻の紗知代さんも、虚血性心不全だった。突然死が話題になっている。
脳卒中や心筋梗塞は、起床後の3時間、仕事の終わった夜8時前後に発症ピークとか。自律神経の乱れで血圧が上昇する。
通勤やオフィスの空調で急速に冷えるはよくない。
大杉漣さんは、急性心不全だが腹部大動脈瘤破裂が疑われている。生存率は25%と言われている。腹部大動脈瘤の危険因子は、高齢、高血圧、喫煙、家族歴と言われ、思い当れば医療機関で検査を受けてほしいと医療関係者は警告している。
工藤日出夫 北本市議会レポート 第144号(2018年6月)
鴻巣行田北本資源組合議会 百条委設置を否決 〜 真相解明遠のく
新ごみ処理施設の用地選定が不透明と 〜 整備費300億円超の可能性に懸念
北本市と行田市、鴻巣市の3市で新設を進める「新ごみ処理施設」の用地取得の過程が不透明と、鴻巣市議会議員が問題提起、一部事務組合(環境資源組合)議会が、5月29日午後5時30分から臨時議会を開き、真相解明を調査する「百条調査特別委員会設置」の決議は賛成4人、反対9人で否決された。
恣意的な選定 百条で解明…
平成27年に決定した場所は、鴻巣市安養寺地区で、鴻巣カントリーに隣接している。この場所は、選定評価で1位であった。
ところが鴻巣市議の調査で、全体で52カ所を調査したと事務局は報告したが、実際は53カ所であった。除かれたのは、評価2位でその差は2点であった。
なぜ除いたかは手続きミスと陳謝したようだが、決定された場所は組合の管理者である鴻巣市長の地元ということで問題視されている。
選定地に農振除外の課題
さらに問題を複雑にしているのが、決定した土地は、「県営かんがい排水事業安養寺地区(堰の改修事業)受益地であるため、平成32年まで農振除外の手続きが出来ない(手続きに入ってからも県レベルで時間が必要)土地」で、事業の開始に大きな影響が出る可能性があると指摘している。
このことを管理者は承知していなかったとしている。そうなら無責任であると言わざるを得ない。
除かれた候補地は、
● 元々は受益地ではないところにあったが、それを受益地内に移動させ、結果として除いている。恣意的と指摘している。
さらに、
● 候補地は洪水ハザードマップで浸水2m~5mに位置し盛り土が必要だが、評価基準の要件に土地整備については考慮されていない。
など問題が多いと言われている。
このように、候補地選定過程における計画建設課の動向は、公の事業の進め方として不適切である。事務局はこれまでの説明で次々訂正している。
このようなことで、議会が地方自治法第100条に基づいた調査が必要と、設置の決議を提出したが否決された。
用地費を除いた整備費が約240億円で、今後300億円を超える可能性もあることから、議員の責任が問われる。北本市議会派遣の金子真理子議員は賛成したが他の3人は反対した。
新教育長に校長退職深谷市在住の清水隆氏を任命
真尾教育長が長期にわたって病気入院で、5月24日に辞職しました。元々6月末が3年の任期でした。
市長は早々と、3月に新教育長の人選をはじめ、辞職をもって議会に提案した。新教育長は、元県校長会会長などされた深谷市在住の清水隆(61歳)氏です。
市長は経歴実績が申し分ないということでしたが、文科省は、議決にあたり議会に所信を述べるべきと通知している。現王園市長は3年前「3年後は所信を述べる機会をつくる」と答弁したが、それを反故にした。
それは答弁の自己否定であり、答弁の信頼性が損なうと、私は「所信を求める決議」を出したが議会は否決した。議会は、市長が自分の答弁を反故にしても良いと認めたことになり、議会の自殺行為。
この決議に共産党は、議運で「先議」議案と決めたことを理由に反対し、否決したことは残念であった(残念)。
工藤日出夫 北本市議会レポート 第145号(2018年7月)
人口と税収減の中の大型公共事業見直し不可避
ごみ処理施設・久保区画整理事業・デーノタメ遺跡保存等々
少子高齢・人口減少は、北本市が抱える最重要な政治テーマであり、かつ現実に対応しなければならない課題である。
人口は2025年 62,000人、2035年 55,000人と推計(社人研統計)され、市税収入は2018年の87憶円から2027年 70億円と、10年間で約17億円減収すると市財政課は推計している。
ゴミ処理に最大470億円?
一方少子・高齢化で子育て・医療・介護等の福祉財源確保は避けられない。そのような中で、現在進行中の「北本・行田・鴻巣の3市のごみ処理施設建設」は、焼却施設等の費用が240億円と計算され、それに用地費、盛土費、道路等の基盤整備費を加えると300億円とも言われ、20年間の維持費170億円を加えると470億円と多額の財源が必要になる。
3市で人口割と言っても、4分の1の120億円は北本市負担。吉見の焼却施設の閉鎖もあり、どう進めるか市民の理解も必要である。
区画整理事業の見直し必須
久保区画整理事業は、平成7年の事業決定から既に20年が過ぎ、予定総事業費110億円の約40%弱の進捗率である。
事業決定の平成7年は、日本の経済は高度成長型からバブルを経て低成長時代になったころであるから、区画整理事業で宅地を供給し、人口増加につながるかは疑問のあった時期でもあったが、当時の議会も積極的に区画整理事業を進めていた。
しかし、現在は人口減少社会になり、また、この地域はデーノタメ遺跡の出土やオオタカの営巣地であったこと。そして国の補助金が計画通りに交付されないなど、今後の進捗に課題は多い。
今後事業完了まで25年ないし30年とすれば、この事業の本来の目的であった宅地の供給により人口増は、もはや夢の多また夢。仮に残りの事業費70億円投入て採算とれるか。地権者の理解をいただき、事業の見直しは不可欠だ。
デーノタメ遺跡(縄文遺跡)は貴重な文化遺産である。一部に、国指定で保存ということも言われているが、ここは区画整理内でかつ都市計画道路(西仲通り線:上尾市から鴻巣市まで、事業費60億円)が計画。
またデーノタメの国指定の事業費は最大100億円が見込まれ、国の補助金があったとしても、事業決定に大きな課題は残っている。
遺跡を記録保存した場合も、調査に数億円単位が予測されている。相当の智慧と決断が必要である。いずれにせよ、住民不在では決められないだろう。
新教育長に清水氏が就任
平成30年第2回定例議会は、6月21日閉会した。今議会で、真尾教育長の病気辞職に伴い、深谷市在住の清水隆氏(62歳)の教育長任命議案に同意し、7月1日から就任する。
この新教育長の任命にあたり、現王園市長が3年前に「3年後の新教育長の任命の時は、候補者に所信を述べさせる」と答弁した。しかし今回それを反故にしたことは、市長答弁の信頼性の失墜であり、議会(市民)軽視で容認できない。
国は、教育行政法を改正し、いじめ等の問題に迅速に対応できるよう教育長の権限を強化した。そのため教育長の任命は議会の同意に改めた。国は地方に、議決には「新教育長の担う重要な職責に鑑み、資質・能力を十全にチェックするため、候補者が所信表明を行った上で質疑を行うなど、丁寧な手続を経ることが考えられる」と通達した。
地方制度をゆがめた
私は、候補者について、経歴しか情報がなく、人柄も、教育ビジョンもわからない。なにより、北本市の教育の方針を知りたかったので、採決前に所信を述べさせるべきと市長に求めたが拒否された。
したがって、3年前の市長の答弁の通り「所信証明を求める決議」を議会に提出したが、賛成8人、反対10人で議会は否決した。
賛成討論はあったが、反対者の意見証明はなく、理由を示すことなく、「市長の答弁反故」を議会は認めた。これでは北本市議会は、今後市長が答弁を「反故」にしてもいいと機関決定したことになる。
執行部のチェック機関である議会の権能は著しく低下したと言わざるえ終えない。制度をゆがめてしまったことは、極めて残念である。
工藤日出夫 北本市議会レポート 第146号(2018年9月)
9月定例議会8月30日開会・平成29年度決算など審議 - 財政持続に議会のチカラを!
平成30年第3回定例議会(9月議会)は、8月30日から9月日26日までの28日間開催されます。市長提出議案は平成29年度決算や条例、補正予算などが提出される。一般質問は18日から行われ、工藤日出夫は「久保区画整理事業の見通し等」を通告する。
いずれにせよ、今議会は決算議会です。決算審査を通じて、未来に持続させる財政をどう構築させるか。無謬(むびゅう)の行政という幻想に、まさに議会のチカラが試されるのでしっかり対応する。
無謬の行政という幻想を断ち切れ! 〜 市税収入は人口減少などで10年後15億円減収
「議員のみなさんは<むびゅうの行政>という幻想に寄りかかっていませんか」
と、会場に響いた講師の一言。
夏の議員研修会でのことである。私は「むびゅう(無謬)」という言葉の意味が分からず、こっそりスマホで検索した。
「無謬とは、理論や判断に間違いのないこと」
となっていた。
私、日本の地方制度は「執行機関(市長)」と「議事機関(議会・議員)」が、対等の立場で「チェック&バランス」を働かせ、市民を代表して市政の誤りを正していくことと考えている。それだけに、市長提出議案には、間違いがあるかもしれない、というスタンスで質疑をしている。
疑を質す「問題意識」を
質疑は、疑を質す事である。それには、常に問題意識を持つことが必要であると認識している。そのため、ややもすれば「市長の反対派」と言われることもあるが、それはある意味「議員である証」と自負している。
市長与党と称し、まさに「無謬の行政」と、議案に無原則に賛成するだけでは、納税者でもある市民の信託に応えられない。熟議が議会の神髄である。
決算審議の課題を次に
平成29年度一般会計及び特別会計決算が示された。今議会の主要議案は決算審議です。平成29年度決算から、本市の財政状況を検証できる。
北本市の財政指標は、少子高齢・人口減少が大きく影響を与えている。例えば市税収入であるが、平成29年度90億円から10年後75億円へと15億円減額する。反面、医療や介護、子育て支援などの福祉財源は増加するが、住民の安心・安全のためには、大きく減額させることはできない。
それだけに、既存の大型公共事業と公共インフラの統廃合など、それに計画されている道路整備などに聖域を設けず改革が必要である。
工藤日出夫 北本市議会レポート 第148号(2018年10月)
9月定例会閉会。平成29年度決算承認。手話言語条例制定
平成30年第3回(9月)定例議会が、9月25日閉会した。
市長提出議案の平成29年度決算は同意された。また、聴力に障がいのある人たちの手話を言語とする「手話言語条例」も可決した。この条例は障がいのある人たちの団体からの強い要請もあり、今議会に提案されていた。
また補正予算についても可決。さらに市民が要請した請願2件も可決した。平成28年12月議会に設置した「新庁舎建設疑惑解明の調査委員会」の最終報告書が議決された。
9月定例会の概要を、以下に述べる。
平成29年度決算額約329億1,700万円承認
北本市議会は9月定例議会で、平成29年度一般会計決算(歳出決算額19,117,915,402円)および5特別会計決算(歳出決算額13,799,791,298円)の合計32,917,706,700円の決算を認定した。他に公営企業会計に変わった下水道事業の決算も認定された。
市税は90億6,454万円で前年比-3億8,318万円。
めざせ!毎日1万歩運動に一人14,230円の経費
この事業は県から2,394万円全額補助金であるが、参加者は1,682人で一人当たり14,230円でした。一人ひとりの健康寿命を延ばす運動は、税金に頼らず自己力で続けたいですね。
手話を言語とする「北本市手話言語条例」制定
聴覚障がいの方々の団体から要望のあった手話を言語とする条例は、全会一致で制定されました。ノーマライゼーション社会への着実に進んでいます。
子ども子育て支援事業の周知を求めた請願可決
中央保育所の立て替えなど、保育に関する通知や情報をオープンにして、市民参画の機会をつくってくださいという保育所父母会からの請願でした。私は賛成討論で「情報共有と市民参画は、民主主義の原理。このような請願が出ることに政治の側は反省すべき」と申し上げました。
議員及び市長の選挙の公費負担の条例改正可決
議員と市長の選挙で、選挙運動のビラの公費負担。これまで議員の選挙ではビラの配布は認められていませんでしたが、来年の選挙から公費で作成費を負担配布できることになりました。
久保区画整理事業とデーノタメ保存に意見多数
久保区画整理事業が遅れているのはデーノタメ遺跡保存が決まらないからと。今議会でデーノタメの遺跡保存と久保区画整理事業について質問が多数の議員が行った。
工藤日出夫 駅前レポート 第1号(2018年10月)
新・北本創生へのイノベーションを探る連載(1回目)
少子・高齢化と人口減少の「ふたごの事実」から目をそらすな
私は3年半前の選挙の時「北本市が危ない」とレポートを出しました。人口減少・超高齢化そして借金財政を指摘しました。市長は代りましたが、この問題は続いています。
事実を率直に受止め、根拠ない「盲信」から現実を確認した改善策(イノベーション)が必要です。
私たちが住む北本市は、ここ10年間地域社会の変化に伴う「双子の課題」に直面しています。
その双子の課題とは、「少子・高齢化」と「人口減少」です。この現象が、双子のように同時
進行していることが、市政運営に様々な課題を投げかけています。
しかし、この課題に的確に対応する具体的・効果的な政策を示せず、今日に至っています。これらの事実を踏まえ、今後の北本創生をご一緒に考えて行きませんか。
減り続ける人口に打開策は
まず下表1です。北本市の人口動態(推計)ですが、平成21年住民基本台帳で70,278人、5年後の平成26年68,400人ですが、平成31年の推計では65,201人と10年間で約5,000人減少すると予測しています。
さらに平成36年62,367人、平成41年58,916人、平成46年52,698人と人口は減り続けると推計しています。

こういう中で、日本創生会議は平成26年に30年後に消滅可能性都市となる市町村を発表し、北本市もその中にあり大きな話題になりました。
本市は少子化も進んでいます。特殊出生率も平成26年1.02で県平均1.31を下回っています。また高齢化率は平成26年27.0%で県平均24.8%(平成27年)を上回っています。
少子化と高齢化と共に、人口の自然減(出生数より死亡数が多い)と社会減(転入者数より転出者数が多い)が同時に10年間続いています。
工藤日出夫 駅前レポート 第2号(2018年11月)
新・北本創生へのイノベーションを探る連載(2回目)
若年者人口の市外流出は人口急増期の反動が一因か !
前号では、北本市が抱える「ふたごの事実」である少子高齢・人口減少の実態を述べました。
そして、その影響は財政の硬直につながり、自治体としての自立(自律)を損なう可能性を指摘しました。
さて、なぜ人口減少が市税減収につながるのかということです。これは、北本市が市制施行後45年にわたり、まちづくりの都市像である「緑にかこまれた健康な文化都市」に起因していると、私は概観しています。
70年代驚異的な人口増
表1は、北本市の昭和45年以降の国勢調査による人口の推移です。
昭和45年に人口が3万人を超え、翌年の昭和46年に市制施行しています。北本団地の入居が始まったのもこの頃です。昭和45年から昭和50年までの5年間で、15,000人の増加です。
その後も平成7年までの20年間で、23,000人毎年平均1,100人増加しました。これは、東京圏に人口が集中し、飽和状態から放射線状に郊外へ人口が移動した高度経済長期の極めて平均的な現象でありました。
市は人口誘導への特別なインセンティブの政策をしなくとも、働き盛りの住民(勤労者)が移住しました。新住民と呼ばれ、わたしもその一人です。
住宅都市で人口11万人へ
当時は道路等の都市基盤整備が追い付かず、いまだに市街化区域に狭隘道路が多数点在しています。人口増加に対応するための乱開発の結果と言えると思います。
このような状況から、好むと好まざるを得ず、北本市は「住宅都市」として成長してきました。
これは必然的に、都市像を「住宅都市」として決めざるを得なかったとわたしは見ています。しかも市は人口増加で市税収入も増え、学校等の基盤整備は必要であったが、人口の増加は成長に大きく寄与したでしょう。
昭和40年代は、市の将来人口を11万人と見積もったことでも、この時期の人口増加は驚異的であったということです。
市は、人口増加とともに、大型商業施設(忠実屋等)を誘致したが工場等の企業誘致には消極的でした。これは市街化調整区域(農業振興地)が多く、商業用地と工業用地が少ないという、都市計画の不備も要因であったと思います。
後部に「土地利用構想図」を添付しましたのでご参照ください。
工藤日出夫 駅前レポート 第3号(2018年11月)
新・北本創生へのイノベーションを探る連載(3回目)
このままだと人口減少が加速し、子どもと若者がいなくなる
連載の1回目は、北本市が抱える「ふたごの事実」である少子高齢・人口減少の実態を述べました。
2回目は、昭和40年代からの人口急増そして平成20年以降の人口減少の動態について述べました。
現在の人口減少は、昭和40年代の人口急増の反動的要素が強く、結果から見ると「必然的」であると言わざるを得ません。しかしそれは、人口動態を専門的に考察・分析すれば十分に予測できたことです。それができなかったことは、政治の不作為と前号で述べました。

下表1は、(一社)持続可能な地域社会総合研究所(所長:藤山浩)が、市町村の人口動態を国勢調査をベースに独自に推計したものです。
この研究所長は、独自開発の分析プログラムにより、人口減少で厳しい予測のある地方で、人口回復の実績を持っています。

今のままでは減少止まらず
2010年と2015年の比較で、4歳以下の人口増減率-19.9%。
小学生人口増減率-8.9%。
10代後半から20歳前半の男性8.4&、女性6.8%と、子ども人口の減少と若者の流出が大きくなっています。
一方、伊奈町と吉川市は人口が増加し、10代後半から20歳前半の男女が転入増になっています。桶川市は、北本市と同様の推移でありますが、数値は北本市に比べ低くなっています。
我々が危機感もって受け止める必要があるのか、30年後の2045年の予測数値です。過去と同様の人口動態であれば、人口増減率-35.1%で約43,000人。
高齢化率45.6%。その上子ども増減率-56%、30歳代男女増減率54%と30年でほぼ半数になるという予測値です。
特に図1のいわゆる「出産可能年齢層(20歳から39歳)」の女性人口が毎年約100人以上減少していく予測です。
表1における20歳代から30歳代女性人口の減少と子どもの減少を裏付けています。

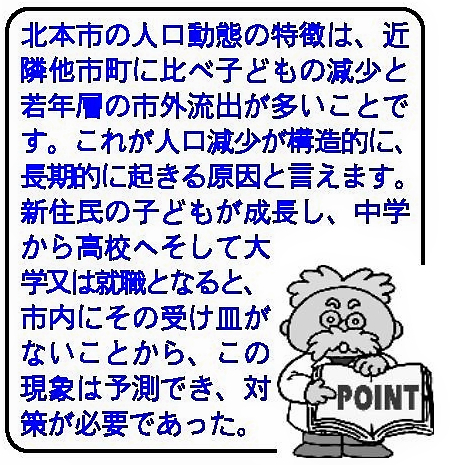
工藤日出夫 駅前レポート 第4号(2018年11月)
新・北本創生へのイノベーションを探る連載(4回目)
少子・高齢・人口減少が危機なのではなく、危機に的確に対応できないのが危機 !
連載の1回目は、北本市が抱える「ふたごの事実」である少子高齢・人口減少の実態を述べました。2回目は、昭和40年代からの人口急増そして、平成20年以降の人口減少の動態について述べました。3回目では、長期的な人口動態予測と幻になった成長戦略としての「県央アクシス計画」について述べました。
ここまで、北本市の人口減少の推移とその原因ともいえる本質が明らかにしました。この傾向は、現在も続き、まさに「危機」に的確に対応できないことが危機であるといえます。
この危機をどう乗り切るのか。ご一緒に考えていきましょう。
バブル崩壊直撃か
第3回目に紹介した「県央アーバンアクシス計画」は、バブルが崩壊した後の平成6年に策定しています。有史以来の経済危機の中ですから、民間企業なら考え直しているでしょう。
この計画の基は県が主導して昭和63年に設立した「県央都市づくり協議会」です。
昭和63年(1988年)はバブル経済前夜で、高度経済成長期でした。しかし、アーバンアクシス計画策定の平成6年以降は、バブル経済が崩壊し成長に大きな陰りが見え、土地神話の崩壊と金融機関の破たん(拓銀、山一証券など)が起きました。
このような状況で、公共事業にも影響が出、高速道路整備に遅れや中断が相次ぎました。
高速埼玉中央道路は中断となり、上尾バイパスも圏央道桶川JCTまでとなりました。また、圏央道の工事は、北本市域にオオタカの営巣が確認されたことから、工事が中断するなど県央アクシス計画の「交通体系の整備」に大きな影響が出ました。
新駅計画とん挫
また新駅は、市の請願駅であり旧国鉄(その後JR)に要望してきましたが、なかなか実施に至る回答が得られない状況が続いていました。そういう中で、市は2度3度と立地に向けて調査・計画を策定したが、決定的な方針を出せる状況には至りませんでした。
そのような中で、圏央道の整備で踏切の廃止に伴い、新駅設置の環境が整ったと、JRから整備に向けた調査可能の方針が平成25年に示されました。
石津前市長はそれを受け、総事業費約72億円(北本市負担約50億円)の新駅立地事業計画を策定し、賛否を住民投票に付しました。結果は、投票者の3分2が反対で白紙となり、現在に至っています。
このように、北本市の成長戦略であったアクシス計画は、バブル経済崩壊等の社会変化に飲み込まれ、途中で見直すこともなく無残にも忘れ去らてしまいました。
しかしながら、この計画を発端にしたであろう「久保区画整理事業」は、途中で見直すこともなく20数年にわたって事業が継続、財政負担等将来に大きな課題として政治決断を待っています。
いずれにせよ、北本市は社会経済の環境変化があったとはいえ、変化に適合した再構築を図ることもなく、成長のチャンスを逸したと言えます。
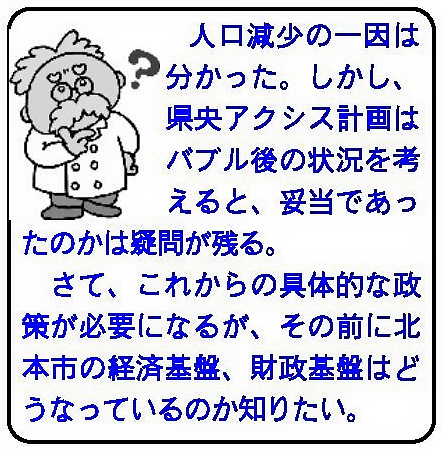
平均年収は減収傾向
それでは、北本市の経済産業力、そして財政の基盤について北本市の統計資料等から見てみます。
先ず、2017年総務省が発表した資料を基に、全国市町村別の平均年数です。北本市は314万9,348円で全国335/1741(2010年は、323万8,050円で198/1741)となっています。平均年収は減収傾向にあります。
桶川市は322万7,593円、鴻巣市は316万9,169円で、1位は東京都港区の1,115万755円でした。
1位の港区の2010年は、943万5,258円ですから、この7年間で大きく伸びています。
また、2010年と2017年の比較で大きく伸びているのが北海道です。猿払村は813万7,339円で3位。ホタテ漁が豊漁でついにランキング3位にまで登り詰めています。北海道の田舎町が平均所得813万円を稼ぎ出している事は驚きでしかありませんと、公表した機関は述べています。
北本市の個人所得は、減少傾向にあります。
工藤日出夫 駅前レポート 第5号(2018年11月)
新・北本創生へのイノベーションを探る連載(5回目, 最終回)
「盲信」による誤った選択と集中から現実に対応したイノベーションに活路を
連載の1回目から4回目まで読んでいただき感謝申し上げます。ここまでは、私の感情でなく、データから読み取った事実を基に述べてきました。
北本市の再生、新しい北本創生には、事実から目をそらし合理的根拠の希薄な、政治家個人の思い付きによる「盲信」でなく、事実に基づく根拠を明確にし、現実を確認した合理的な「選択と集中」へと転換させ、イノベーションに活路を求めて行くべきです。
現実無視の“盲信”による選択と集中は、まさに間違った一生懸命で「幽霊に大砲を打ち込む」ようなもので、成果が得られないのは当然の帰結です。ここまでの4回述べたことをもとに、現実(事実)に対応したイノベーションについて述べます。
皆様のご意見をお待ちしています。
子育て支援で驚異的な回復
北本市の少子高齢・人口減少については、第1回から4回までの論考でおおよその傾向を述べました。ここでは、この問題の本質を探り、その対策について考察します。
まずは、少子化と若者の動態についてです。
少子化(出生率)の改善は、一地方自治体の政策では極めて困難であります。このような中で沖縄県は、1人の女性が生涯に産む子どもの数を推定する合計特殊出生率が1.95で32年連続で全国1位となっています。
一方なぜか、離婚率も14年連続全国第1位でした。相関関係があるかはわかりません。
また、過疎地の自治体(岡山県奈義町)が、特殊出生率を2.81と驚異的に伸ばした事例もあります。平成の大合併から取り残され、人口減少に対応するため徹底した子育て支援政策を実行した結果だそうです。
兵庫県明石市も同様に子供と人口を伸ばしました。
財源生出し子育てに集中投資
共通しているのは、合理的な裏付けをもとに財源を、子育て支援に「選択と集中」した首長の政治決断です。
それを国家政策で行い、出生率を驚異的に回復させたのがフランスです。
消費税引き上げで保育料・幼稚園授業料無償化を言いながら、一部を地方自治体にも負担させようと「せこい」考えでは日本の少子対策では、V字回復は難しいでしょう。
私は、子育て支援の新しい政策に、まとまった財源を生み出し、子育て世帯の経済的負担の軽減と子育てを社会の責任、働くことととの両立、子育てが親の自己実現につながる文化・環境をつくることが重要と考えています。
工藤日出夫 北本市議会レポート 第149号(2018年12月)
2018年 今年も工藤日出夫の活動にご理解いただき感謝です
平成最後の師走です。今年も残り少なくなりました。この一年、工藤日出夫の議会活動・政治活動に過分にご理解・ご支援いただきありがとうございました。
今年は、一昨年からの「新庁舎等の公共工事の調査特別委員会(100条委員会)」の調査に没頭し、報告書にまとめました。二度とこのようなことが起きないよう、現王園市長に再発防止策(地方公務員法等コンプライアンスの強化等)と損害賠償請求の勧告をしました。1年8カ月に及んだ調査でしたが、私にとってはかけがえのない経験となりました。
さて4年前の年末は、人口減少、借金の増額、消滅可能性都市の公表などで「北本市が危ない!」と、強い危機感を持って年末を迎えていました。その危機感は、市長が代った4年後の、今年の年末も同じ気持ちでいなければならないことに、議員として「悔い」と「反省」をしています。
来年は、4月に統一地方選挙(市長・市議・県議)、夏には埼玉県知事と参議院選挙と、北本市の、埼玉県のそして日本の未来を決める、大変重要な選挙が行われます。市民のみなさまの判断が、皆様の明日、子ども若者の未来を決定します。ぜひ投票所に足を運び、大切な1票を投じてください。
今年一年お仕事に、余暇に、家庭の維持に、子育てにお疲れまさまでした。来年も、みなさまにとって健康で、お幸せな一年になるようお祈りいたします。
北本市議会議員工藤日出夫
12月議会閉会 〜 市長の再選出馬受け保守系議員含め議会荒れ模様の印象
平成30年第4回定例議会が、12月14日閉会しました。今議会は、これまでと議場の雰囲気が一転した印象が強かったです。
これは、11月21日の市長記者会見で「来年4月の市長選挙に、再選目指して立候補を表明した」ことが影響していると思いました。
これまで、穏やかな発言が多い保守系の議員数人が、言葉を荒げ市長のこれまでの政治姿勢を厳しく指弾しました。中には、再選を支持できないとか私利私欲とか、思いがけない言葉が出ていました。
私たち会派は、石津市長時代から続く市政の混迷と停滞を打破するには、事実に基づかない「盲信的」政策推進から、事実を確認した「選択と集中」に変え“市政のイノベーション”を進めるリーダーを求めています。
現王園市長が、再度この難局を突破する決意を証明したことに大いなる期待と敬意をもって、保守系議員の一般質問(再選に向けた決意)を注視しました。

