Yes We Can 〜 私たちはできる 〜 自尊・共生のまち「きたもと」を
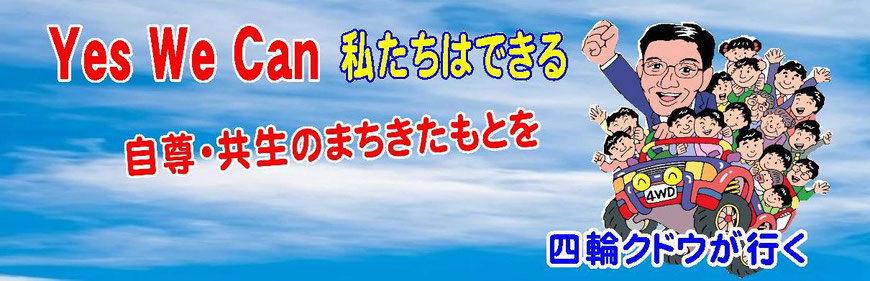
くどうひでお 公式Twitter 〜 ぜひフォローしてください !
お知らせ : 市民の力「わいわいサロン」開催のご案内
市議会会派市民の力は、市民が抱える生活課題について、市民の皆さんと一緒に考え、政治の場で解決しうる課題について参加者との会話と対話により、問題意識を共有する場「わいわいサロン」を定期的に開催しています。
4月19日(金)9:30~文化センター第3会議室 テーマは=地域医療をかしこい患者目線で考える=
今年4月から「働き改革」がスタートします。大学病院等の医療機関に勤務する医師はオーバーワークと言われています。勤務医の働き方で、これ迄とは違った地域医療の問題が生じます。かしこい患者になることは、地域医療を維持発展させるキーワードです。一緒に考えてみませんか。申し込み不要です。ご参加お待ちしています。
最新の北本市議会レポートです
工藤日出夫 北本市議会レポート 第171号 / 会派「市民の力」機関紙新刊第3号 (2024年3月)
令和6年第1回定例会(3月議会)全提出議案議了し閉会
令和6年度 一般会計外5特別会計等予算 可決
令和6年第1回定例会は2月20日(火)開会。
3月22日(金)市長提出33議案と議員・委員会提出6議案すべてを議了(可決)し閉会しました。
今議会は市長提出の令和6年度一般会計予算と5特別会計・公営企業会計(下水道)予算の外条例制定・改正、教育委員の任命。令和5年度の補正予算。議員提出の請願2件が審議されました。
請願は「学童保育室の指定管理に関する請願」と「スクラップヤードの騒音等の請願」は採択されました。
主な議案の審議詳細は以下に述べます。
一般会計予算 過去最大の積極予算
表1は、令和6年度北本市一般会計及び特別会計(公会計)予算の総括表です。

歳入・歳出合計は407億9,088万2,000円です。一般会計は242億1,000万と市制施行後最高の予算規模となりました。
民生費(医療福祉・子育て等)108億9,432万と予算全体の45%と、少子高齢社会を反映しています。
また特別会計の久保区画整理事業は、事業の遅れと都市計画道路等の課題を含め都市計画道路の整備を重点に前年度比3億7千万円と増額しました。
一般会計の歳入では、市税は前年度比減収で、人口減少と高齢化で今後も減収の見込みです。国からの地方交付税や地方消費税交付金等の交付金と国庫支出金、県支出金は増額しています。
また、ふるさと納税(寄付金)を経常収入にしていますが、確定財源とは言えない分不安さが残ります。
北本市議会レポートのバックナンバーは「活動」ページで お読みいただけます。
